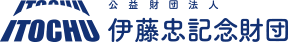- 現在のページ:トップページ
- 事業概要
- 子ども文庫助成事業
- 文庫のひろば
- レポート・コラム・お知らせ
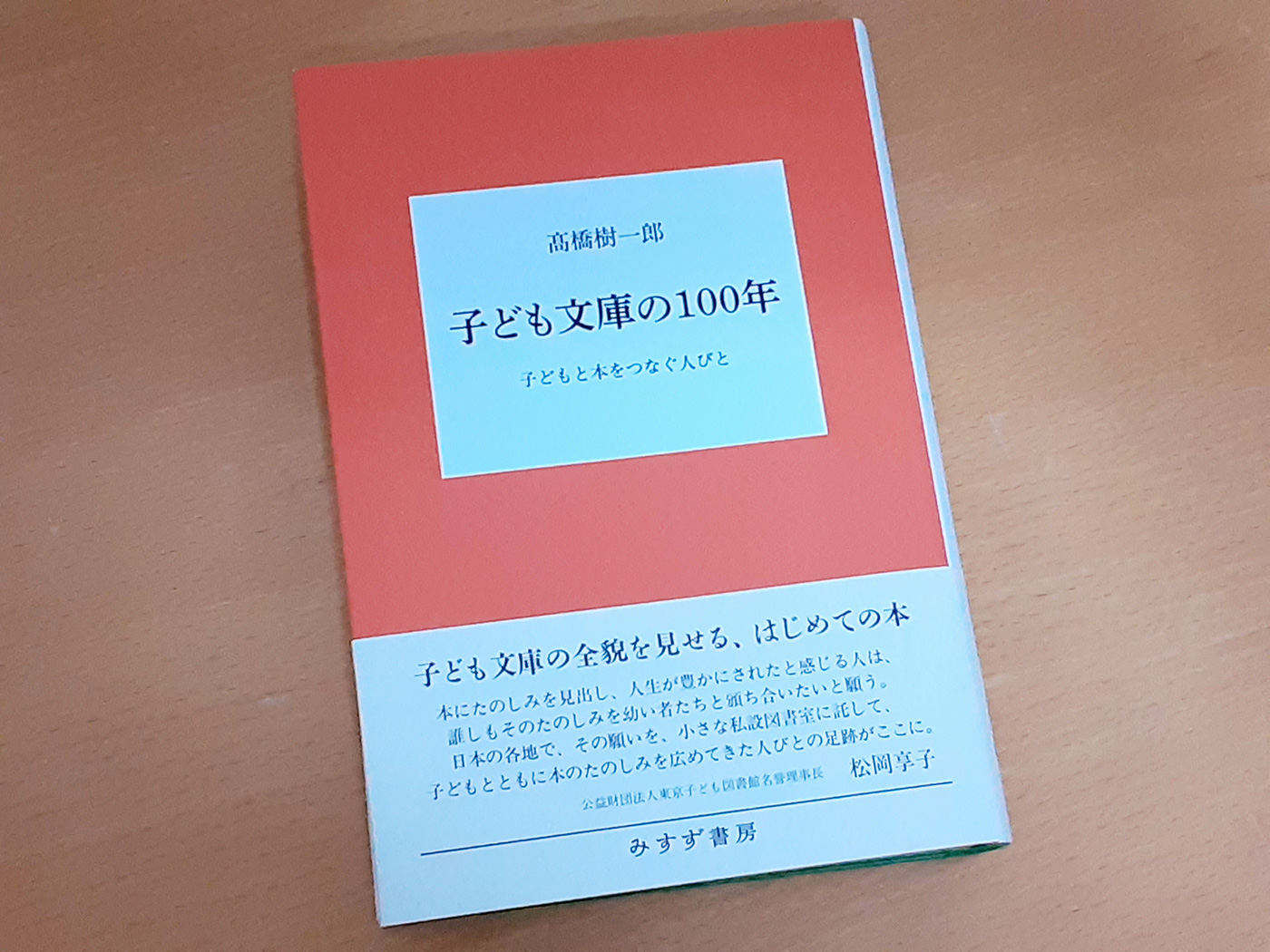
子ども文庫―私設の子ども図書館―は明治時代の終わり頃から各地に在りました。例えば、伊藤忠商事本社から徒歩10分ほどの場所(表参道駅近く)には、明治末年から大正にかけて、子どもの本の作家が開いた文庫がありました。そして―これは、強調して記すべきことですが―二代目伊藤忠兵衛氏も、お母様の古稀を記念して「済美会図書館」を設立されています(これは大人向けの図書館でしたが)。
子ども文庫は、戦後その数が増え、80年代後半には全国に4000以上もありました。現在でも1000以上も存在します。
松岡享子先生の投稿で触れられている「子どもBUNKOプロジェクト」では、こうした子ども文庫が果たしてきた役割や現状について調査をしました。
調査を通してあらためて感じたのは、文庫の「成果」は、貸出冊数や利用者数といった数字だけでは表せないということでした。
例えば、訪れた文庫でお話を伺った際に、引きこもりで学校に行けなかった子どもが、文庫に毎週のように通ってきたという話を何度か耳にしました。口もきけなかったその子が大きくなって、文庫を手伝ってくれた。後年、立派な青年になったその子が挨拶に来てくれたというのです。
社会が無軌道に加速していった時代、居場所がなかった子たちにとって、文庫は、自分のリズムでゆっくりと息をつける唯一の場所だったのでしょう。そして、文庫で出会った本は、その子の心の深いところにおさまり、目には見えないけれど、確かな支えとなっていたのでしょう。
今は何でもすぐに「数値化」し、活動の成果やら目的達成度を数で表します。もちろん、経済活動では、綿密に事業計画を立て、限られたリソースをしかるべきところに配置し、その結果得られた利益が正当なものかどうかを示す指標が必要です。しかし、すべてが計算し尽くされ、規格外や想定外の出来事をまったく許さない社会で人は生きていけません。
近年、地域での「サードプレイス」の重要性が指摘されています。家でも、学校(職場)でもないもうひとつの場所。自分の社会的・経済的価値や能力・地位を気にせず人と交流できる場所。それはよく考えてみると、子ども文庫そのものではないでしょうか。
地域の人々が、自由な発想で生み出し、自由に運営する地域の小さな図書室は―おはなしや読み聞かせグループの活動もそうですが―その役割を数値で「見える化」できないものの、地域の子どもを育む場として、まだまだ大きな意味を持つのではと思います。文庫の数は近年減っていますが、「まちライブラリー」の活動の様に、私設の図書館を作る動きが見られるのも、何かを示唆しているのかもしれません。
最後になりましたが、私の人生を大きく方向付け、貴重な業務を担わせて頂いた伊藤忠記念財団には感謝の思いしかございません(私は、以前財団がなさっていた海外留学の奨学金を頂いております)。これからも、子どもと本の世界にかかわる人々へのご支援を続けられることを期待いたします。

髙橋樹一郎 プロフィール
1969年生まれ。慶應義塾大学図書館情報学科卒。マクギル大学大学院図書館情報学科修士課程修了。
現在、奈良県天理市立図書館館長補佐。